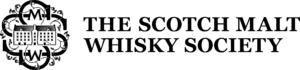ウイスキーの品質特徴として一目でわかるのが琥珀色である。ポットスチルで蒸留した直後のモルトウイスキーは無色透明である。ウイスキー以外の蒸留酒 ブランデー、ジン、ラム、テキーラ、焼酎も全て蒸留した直後は揮発性の無い色素成分は含まない。同様に蒸留されることで甘辛酸渋苦に関わる味わい成分も基本的には含まれることはない。そのようなホワイトスピリッツに甘辛苦酸などの印象を受けるのは、揮発した香気成分が、その味わいを連想させるからである。ポットスチルで2回蒸留して得られるこのウイスキーの素を本溜液という。スコッチではニューメイクやニューポットと呼ぶが、日本のウイスキーの父竹鶴政孝により「本溜液」と訳されている(以下に登場する蒸留用語も竹鶴政孝訳)。1回目の蒸留(初溜)でホップの入っていないビール様のアルコール度数が7〜8%程度の醗酵醪を蒸留する。これは大雑把にアルコールと付随する香気成分を回収する目的である。醪全容量の約1/3の蒸留液を得ることができる。釜に残った2/3の残液にはアルコールは含まれない。約1/3の蒸留液のことを初溜液(ローワイン)と呼ぶ。アルコール度数は逆に3倍濃縮されて21~24%となる。この初溜液を再度ポットスチルに投入して蒸留(再溜)する。今度は香りの成分を分留する目的なので時間をかけてじっくりと蒸留する。出始めのところには不快な刺激臭や夾雑成分が出てくるので別取りする。この液体は前溜液(フォアショット)と呼ぶ。その後良質な香気を伴う留液の部分だけを集めて本溜液とする。やがて再留の後半に不快な香気を伴う部分にさしかかる。この時のアルコール度数は約60%。この不快だがアルコールがまだ含まれる留液部分をまた別取りする。この液体は余溜液(フェイント)と呼ぶ。各蒸溜所はこの本溜液から余溜液への切り替えタイミング(カット)をノウハウとして持っている。スコットランドでは本溜液はスピリッツレシーバー(受けタンク)に、前溜液と余溜液はフェイントレシーバーに合一されて収まる。次々と蒸留が繰り返され、新たに蒸留された初溜液も、このフェイントレシーバーに収まる。つまり次回からの再留にはこのフェイントタンクに合一された、前溜液、余溜液、初溜液の混合液を再溜釜に入れれば良い。これが連綿と繰り返されるのである。ちなみに「初溜液」という言葉は、一回蒸留で製品化する焼酎製造では出初めの部分を指す。ウイスキーでの前溜液のことであるので紛らわしい。モルトウイスキーのこの2回の蒸留方法は世界の蒸溜酒のスタンダードになっており、この技術が確定したのはなんと16世紀に遡る。1559年出版のTreasure of Evonymous(Peter Morwyng著)には、2回蒸留や3回蒸留、ミドルカットの手法や蒸留器具の構造などが書かれているそうだ。サイズ的には20L前後で大きくとも180Lであった。当時ルターに始まるイングランド宗教改革がスコットランドに波及し、教会の再構築と修道院(ケルト教会系?)が解体された。その際多くの修道僧がビール醸造、蒸留業者、錬金術師、医者になっていったため門外不出の多くの蒸留方法の知見が広く拡散した。そのため16世紀ヨーロッパでの蒸留技術の最先端を走っていたのはスコットランドだったそうだ。
<注:用語において、「蒸留」と記すのは科学用語のため現代かな使い。「蒸溜」と記すのは竹鶴政孝の訳語に敬意を表した固有名詞として旧かな使いにしております>
ウイスキー概論3 〜蒸留のこと〜

ABOUT ME